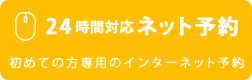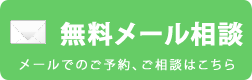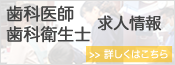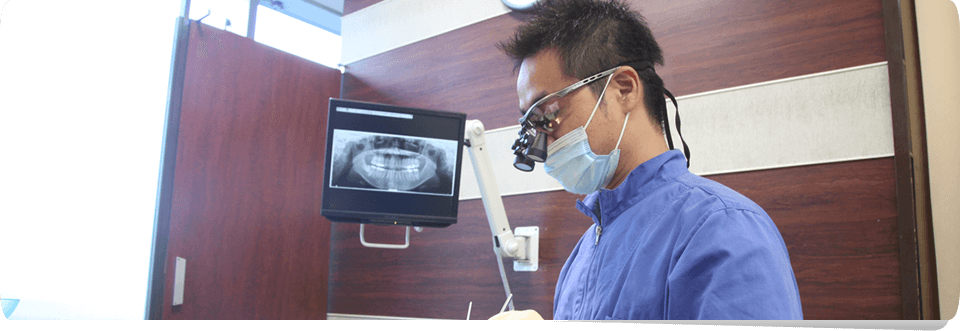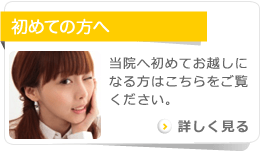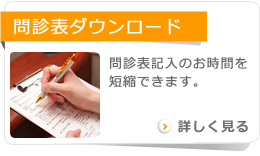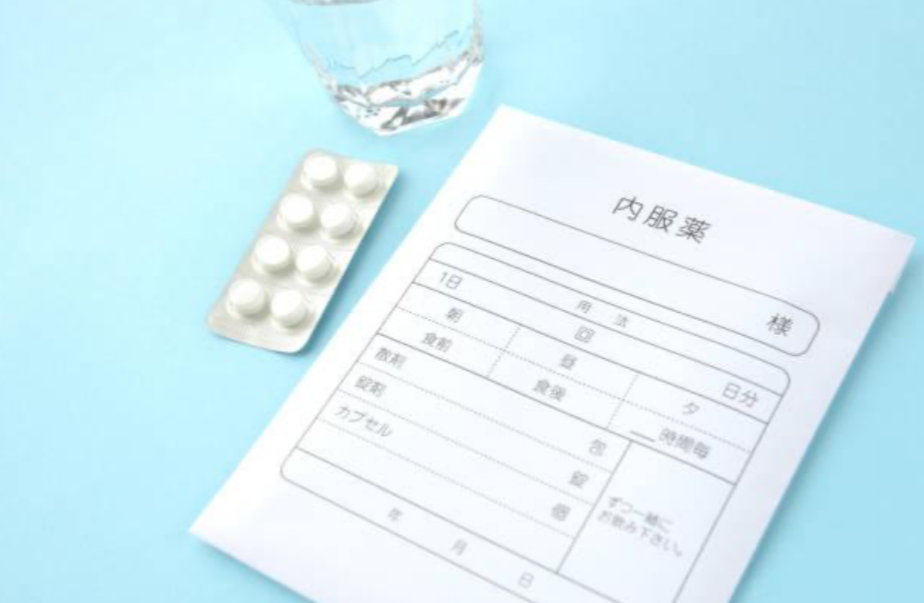こんにちは。
関原デンタルクリニックです。
虫歯は「甘いものを食べるからできる」と思われがちですが、実はそれだけが原因ではありません。
毎日の食事内容だけでなく、食べる時間や回数、食べ方の習慣が虫歯の発生に大きく関わっています。
今回は、虫歯ができる仕組みをふまえながら、虫歯リスクを高める食事習慣と、その対策についてご紹介します。

虫歯の発生要因 脱灰と再石灰化のしくみとは?
私たちの歯はとても硬そうに見えますが、実は日々少しずつ溶けたり修復されたりしています。これを「脱灰」と「再石灰化」と呼びます。
食事をすると、口の中の細菌が糖分を分解して酸を作り出します。
この酸によって歯の表面からカルシウムやリンなどのミネラルが溶け出す現象が脱灰です。
一方で、唾液には歯を守る働きがあり、溶け出したミネラルを歯に戻す作用があります。これが再石灰化です。
通常は脱灰と再石灰化がバランスよく繰り返されているため、すぐに虫歯になることはありません。しかし、脱灰の時間が長く、再石灰化が追いつかなくなると、歯が徐々に弱くなり虫歯へと進行してしまいます。
虫歯リスクが上がる食事の特徴
虫歯のリスクを高める大きな原因のひとつが「ダラダラ食べ」です。
長時間にわたって少しずつ食べたり、間食を何度も繰り返したりすると、そのたびに口の中が酸性になります。
酸性の状態が続くと歯が溶けやすくなり、再石灰化が起こる時間がほとんどなくなってしまいます。
また、食べる量よりも食事や間食の回数が多いことが問題になる場合もあります。
少量であっても回数が多ければ、その分脱灰の回数が増えるため、虫歯リスクは高まります。
甘いお菓子やチョコレートだけでなく、ジュース、スポーツドリンク、砂糖入りのコーヒーや紅茶なども注意が必要です。
虫歯リスクを減らすための食事習慣

虫歯予防のためには、食事や間食の回数を意識することが大切です。
間食は時間を決め、ダラダラ食べを避けるようにしましょう。
食後に水やお茶を飲むことで、口の中に残った糖分や酸を洗い流す効果も期待できます。
また、よく噛んで食べることも虫歯予防につながります。噛むことで唾液の分泌が促され、再石灰化が起こりやすくなります。
特に就寝前の飲食は注意が必要です。寝ている間は唾液の分泌量が減るため、虫歯菌が活動しやすい環境になってしまいます。
フッ素応用の必要性と効果
虫歯予防に欠かせない成分がフッ素です。
フッ素には歯の表面を強くし、酸に溶けにくい歯質を作る働きがあります。また、脱灰された歯の再石灰化を助け、虫歯菌の働きを抑える効果もあります。
毎日のセルフケアでは、フッ素入り歯みがき粉を使うことが基本です。
年齢や虫歯リスクに合わせて適切な濃度のものを選ぶことで、より効果的な予防につながります。
さらに、歯科医院で行う高濃度フッ素塗布は、歯の表面に直接フッ素を届けることができ、より高い虫歯予防効果が期待できます。
特に生えたばかりの歯は質が弱く、虫歯になりやすいため、定期的なフッ素応用が重要です。
お子さまはもちろん、虫歯になりやすい大人の方にとってもフッ素は歯を守る心強い味方といえるでしょう。
まとめ

虫歯を防ぐためには、歯みがきだけでなく、食事の仕方を見直すことがとても重要です。
ダラダラ食べを控え、食事や間食の回数を意識し、唾液の力を活かした生活習慣を心がけましょう。
そこにフッ素を上手に取り入れることで、虫歯のリスクは大きく下げることができます。毎日の小さな積み重ねで、将来の歯の健康を守りましょう。
日付: 2026年2月2日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ, 毎日の食事が歯を守る?虫歯と食べ方の意外な関係